歩くときフラフラ体が定まらないときやいきなり一歩が大きく出すぎて転倒しそうになる、または物を目的の場所まで運べない時や力加減がわからないような時は失調を疑いましょう。
小脳の障害だけでなく感覚障害や脊髄の障害でも失調症状があらわれるときがあります。
失調の定義として「運動麻痺を伴わないこと」とありますが、左右で比較すると明らかな麻痺が見られることが多いです。
企図振戦、測定障害、失調様歩行、失調様発話、力の調節ができない、反復拮抗運動障害など特徴のある動作が見られ、筋緊張は低下しています。一つ一つ症状に合わせて動作の試験を行い確認しましょう。
手回内・回外試験 hand pronation supination test
軽く肘を屈曲し、手の回内回外をできるだけ早く反復するようにします。両側同時に行うと、障害側の症状が増強され異常が目立つ場合があります。うまくできない場合は反復拮抗運動障害(dysdiadochokinesis)と判定されDDK(+)と記載します。
鼻指鼻試験 nose-finger-nose test
患者さんの第2指を検者の第2指の指先と患者さんの鼻のあたまとの間を行き来する動作を繰り返します。
測定障害(dysmetria) は指が正確に到達するかで判定します。
企図振戦(intention tremor) は目的物に近づくほど著明になることで判定します。
運動分解(decomposition) は指を自分の鼻に持っていくときに肩関節が屈曲してから肘が屈曲を始める現象のことです。
踵膝試験 heel-shin test
仰臥位で踵を反対側の膝に正確に乗せ、すねに沿って足首までまっすぐ踵をすべらせる検査です。まっすぐ円滑にできず速度が変化し、左右に動揺するのは測定障害によるものと考えられます。
膝打ち試験 knee pat test
仰臥位で踵で反対側の膝を叩いてもらいます。踵が正確に膝につかず左右にずれ、上下の運動の幅が大きくずれ不規則となった場合、測定障害と反復拮抗運動による運動失調と判定します。
Stewart-Holmes反跳現象
患者さんの前腕に検者は抵抗を与え、患者さんの胸部に向かい強く肘を屈曲するように指示します。その後、検者はいきなり手を放します。
正常であれば胸を打つことはありませんが、筋トーヌスの低下があると自分の胸を強く打つことになります。検者は胸を打たないように反対の手で患者さんの手を受け止めます。
体幹運動失調 trunk ataxia
患者さんをベッドに深く坐っていただき両足を床から離します。その時上体が不安定になります。
Scale for the assessment and rating of atasia (SARA)
SARAについての解説をしています
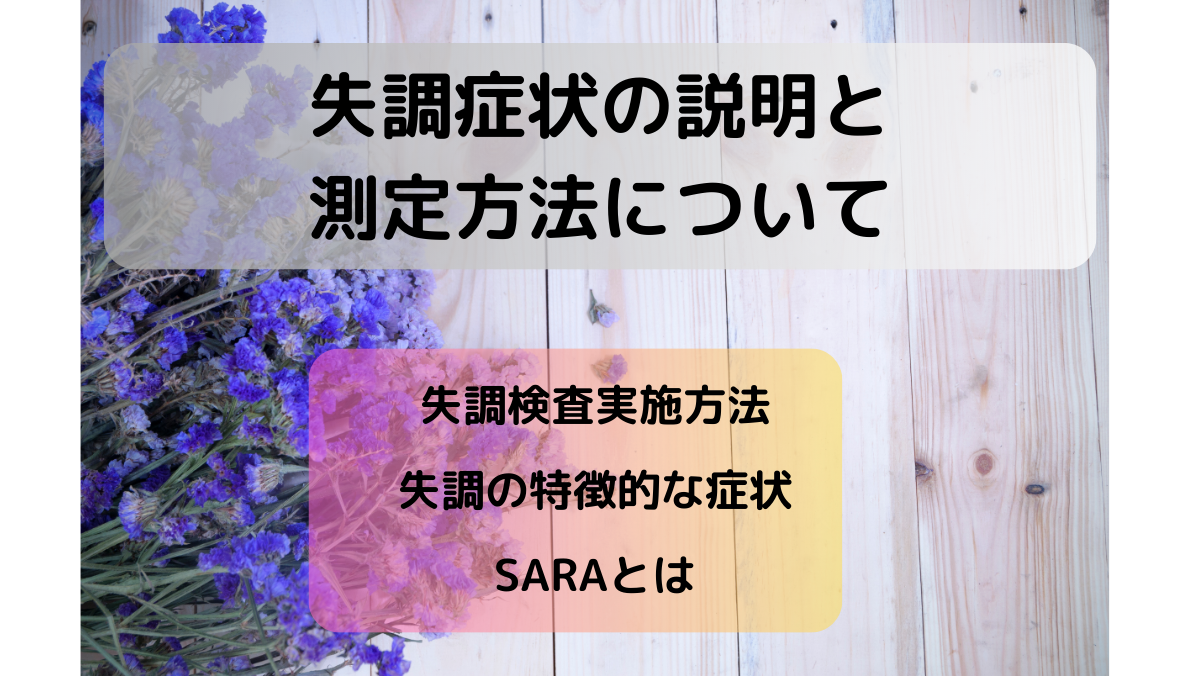
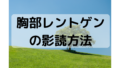

コメント